色の資格のまとめ
「色に関する資格」は、色彩検定、パーソナルカラー検定、カラーコーディネーター検定、色彩士、イメージコンサルタント、など複数あります。
色について本格的に学びたい!似合う色を見つけたい!キャリアアップを目指したい!将来カラーコンサルタントとして独立したい!と考える方にとって、色の資格への挑戦はうってつけです。
とは言っても、種類が多いと「どう違うの?」「結局どれが良いの?」「どの資格がおすすめ?」「難しい?」「私でも合格できるかな?」と疑問も浮かびますよね。
そこで、このページでは主な色の資格をリストアップして、資格の特徴、試験制度、試験日程、受験料などを比較できるように一挙にまとめました。また、私自身もいくつかの資格の1級は取得しましたから、勉強方法についてもご紹介します。
色の取得を考えている方は、ぜひ参考にご覧ください!
色の資格の一覧表
まずはじめに、日本で取得できる主な色の資格・主催団体を一覧表にまとめました。
| 資格名 | 主催 | 開始年 |
|---|---|---|
| 色彩検定 | AFT (公益社団法人色彩検定協会) |
1990年 |
| カラーコーディネーター検定 | 東京商工会議所 | 1995年 |
| カラーマスター色彩士検定 | ADEC (全国美術デザイン教育振興会) |
1997年 |
| 色彩技能パーソナルカラー検定 | JPCA (NPO法人日本パーソナルカラー協会) |
2003年 |
| 色彩活用パーソナルカラー検定 | J-Color (一般社団法人日本カラーコーディネーター協会) |
2010年 |
| 色彩活用ライフケアカラー検定 | J-Color (一般社団法人日本カラーコーディネーター協会) |
2006年 |
| パーソナルカラリスト検定 | 一般社団法人日本カラリスト協会 | 2005年 |
| デジタル色彩士検定 | JCI (日本カラーイメージ協会) |
2008年 |
| カラースタイルコンサルタント | CSCA (全日本カラースタイルコンサルタント協会) |
2012年 |
| パーソナルカラー実務検定 | 一般社団法人ICBI (パーソナルカラー実務検定協会) |
2013年 |
| オーラソーマ資格認定講座 | OAU (株式会社和尚アートユニティ) |
1993年 |
「色に関する資格」はいくつもあって、それぞれ別の民間団体が主催しています。現時点において、色の資格に国家資格はありません。
色彩検定やカラーコーディネーター検定は有名ですから、「なんとなく資格に興味がある」といった方でも、耳にしたことがあると思います。また、パーソナルカラー検定もご存知かもしれません。ところが、パーソナルカラーに関する検定試験は少なくとも4種類。そのほか、色彩士やデジタル色彩士という名称の資格もあります。
さらに、一般試験ではなく専門講座を受講して得られるカラースタイルコンサルタントや、オーラソーマというイギリスで生まれた色を用いた心理探究の認定資格もあって、本当に色の資格はさまざまです。
このように資格認定制度がいくつもあることが、「どれがいいの?」「役立つ?」「肩書としての信頼度は?」「難易度は?」などの疑問を生じさせる理由となっています。
色の資格ごとの特徴を解説【最新版】
次は、上でリストアップした色の資格ごとの特徴・等級制度・試験方式・受験料などを順にご覧ください。(2025年時点の情報です)
色彩検定

「色彩検定」は、公益社団法人色彩検定協会(AFT)が主催する、色の資格のなかではもっとも古くからある資格です。文部科学省後援で信頼度も高く、色について基礎から実用知識まで総合的に学ぶことができます。学んだ知識と資格は、趣味はもちろん仕事において、アパレル、インテリア、メイク、デザイン、広告ほかさまざまな業界にて役立ちます。
| 名称 | 色彩検定 |
|---|---|
| 主催 | 公益社団法人色彩検定協会 |
| 備考 | 文部科学省後援 |
| 公式 | https://www.aft.or.jp/ |
| 等級制度 | 3級、2級、1級、UC級 |
|---|---|
| 受験方法 | 全国の会場でのペーパーテスト(PBT方式) |
| 試験方式 | 3級:マークシート 2級:マークシート+記述 1級一次:マークシート 1級二次:記述(一部実技) UC級:マークシート |
| 受験料 | 3級:7,000円 2級:10,000円 1級:15,000円 UC級:6,000円 (税込) |
| 試験時間 | 3級:60分 2級:70分 1級一次:80分 1級二次:90分 UC級:60分 |
| 試験日程 | 年2回(夏期:6月/冬期:11月) |
| 受験資格 | 制限なし(全級併願可) |
色彩検定には4つの等級があります。3級から1級までの基本の3段階に加えて、2018年に新しくUC級(ユニバーサルカラー級)というものが新設されました。UC級は、色覚の多様性(いわゆる色覚特性を持つ、遺伝的に色の見分けがしにくい方々や、高齢で見え方が変化した方々)に配慮した色遣いやデザインの学習に特化した内容です。
3級は色の基礎知識と、PCCS(ピーシーシーエス、日本語では日本色研配色体系)という、日本色彩研究所が開発した色を整理分類した仕組みについて学びます。PCCSの色見本を用いた配色の習得が、2級、1級まで通して色彩検定の肝となるところです。
2級は、3級の内容にさらに専門的な要素を加えた応用編です。そして1級は、色の知識全体や配色術を日常や仕事の現場で活かせるプロレベルです。
色彩検定の受験方式は、指定の試験会場にて実施されるペーパーテストです。会場は、北海道から沖縄まで各都市にあります。試験当日は会場に行って指示に沿って受験します。
3級、2級、UC級はマークシートおよび記述問題の試験一発勝負。1級はマークシートによる1次試験と、色見本を指示に沿って組み合わせて貼り付けたり、説明文を記述する二次試験(実技試験)もおこないます。
どの級も性別・年齢問わず誰でも受験でき、併願も可能です。色彩検定の試験は開始時刻が級ごとに違うため、同日に3級、2級、UC級などまとめて受験できます。ただし、受験申込の時点で併願を希望しなければいけません。3級の申込後に改めて2級を追加申込すると、受験会場が別々になってしまって物理的に受験不可となってしまうおそれがあります。
試験は年に2回、6月(夏期)と11月(冬期)の実施です。夏期試験は、3級、2級、UC級を受験できます。冬期は1級を含む全級を受験できます。
つまり、1級は年に1回のみ挑戦でき、夏期試験では受けることができません。また、1級では一次試験に合格した方のみ、同年の12月に実施される二次試験に進めます。なお、一次試験に合格して二次試験で不合格だった場合、翌2年間は一次試験をパスして二次試験のみ挑戦できます。
試験終了後、合否通知書とともに合格者には合格証書と資格証が届きます。
カラーコーディネーター検定

カラーコーディネーター検定は、東京商工会議所が主催する、1995年にスタートした色の資格です。色彩検定に次いで2番目に長く実施されている歴史ある資格で、学習を通じて特に実務・ビジネスに活用できる色彩知識を習得することができます。最初は3級、2級、1級という等級区分でしたが、2020年にスタンダードクラス/アドバンスクラスの2段階制にリニューアルされました。
| 名称 | カラーコーディネーター検定 |
|---|---|
| 主催 | 東京商工会議所 |
| 備考 | 2020年に制度リニューアル |
| 公式 | https://kentei.tokyo-cci.or.jp/color/ |
| 等級制度 | スタンダードクラス アドバンスクラス |
|---|---|
| 受験方法 | CBT方式/IBT方式から選べます |
| 試験方式 | 両クラスともマークシート(多肢選択問題) |
| 受験料 | スタンダードクラス:5,500円 アドバンスクラス:7,000円 (税込) |
| 試験時間 | 両クラスとも90分 |
| 試験期間 | 年2期 6月下旬から7月上旬 10月下旬から11月上旬 |
| 受験資格 | 制限なし(両クラス併願可) |
カラーコーディネーター検定は、2019年までは3級、2級、1級の3等級制度でした。また、1級は「ファッション色彩」「商品色彩」「環境色彩」の3分野に分かれていて、合格すればその分野の1級資格を取得できる、というものでした。2020年にこの制度が「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」の2等級制度にリニューアルされ、スタンダードは基礎知識全般、アドバンスは従来の1級各分野を統合した内容となっています。
また、従来は「CICC」という独自の色のシステム(表色系)を用いていましたが、2020年以降は色彩検定と同じPCCSを用いて出題されます。そのため、以前に比べると色彩検定との同時学習もしやすくなったと言えるでしょう。
試験制度の刷新とともに、受験方法も変更となりました。CBT(Computer Based Testing)は、全国約300ヶ所の試験センターに設置してあるパソコンから受験する方式です。試験の開催期間中から、自分で都合の良い日時と会場を選んで、当日現地に行って受験します。
もうひとつIBT(Internet Based Testing)は、自宅やオフィスなど、自分のパソコンを使って受験する方式です。東京商工会議所が定める仕様のパソコンや環境を用意して、当日はモニターのカメラを起動し、案内員の指示に沿って受験します。
このどちらかの方式を選べるため、従来よりも受験しやすくなりました。(ほかの資格の多くも、CBT/IBT方式を採用しているので、この先も登場します)
カラーコーディネーター検定は特にビジネス、実務に役立つ色彩知識の習得を念頭に、色の知識を仕事に活用する方法、カラーコンサルタントの実務フローなども出題範囲です。公式テキストからはそれらの内容もしっかり学べて、アパレル、インテリア、広告、そのほか色に関わる仕事をしている人や、独立・副業を考えている人にとって大いに参考になります。
色彩技能パーソナルカラー検定
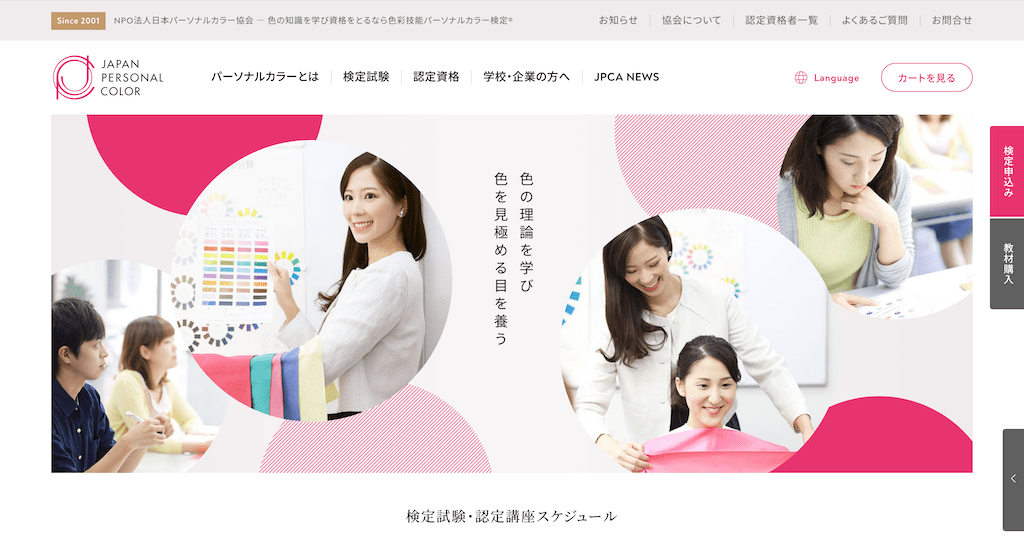
色彩技能パーソナルカラー検定は、NPO法人日本パーソナルカラー協会(JPCA)が主催する、「パーソナルカラー」の理論やカラーコンサルタントとして活動するための実践知識を習得できる色の資格です。日本で最初に発行されたパーソナルカラー関連の資格で、2003年に第1回の検定試験が実施されました。
| 名称 | 色彩技能パーソナルカラー検定 |
|---|---|
| 主催 | JPCA(NPO法人日本パーソナルカラー協会) |
| 備考 | 日本で最も古いパーソナルカラー検定 |
| 公式 | https://www.p-color.jp/ |
| 等級制度 | モジュール1(初級) モジュール2(中級) モジュール3(上級) |
|---|---|
| 受験方法 | CBT方式 |
| 試験方式 | マークシート(多肢選択問題) |
| 受験料 | モジュール1:7,700円 モジュール2:8,800円 モジュール3:12,100円 (税込) |
| 試験時間 | モジュール1:60分 モジュール2:70分 モジュール3:60分 |
| 試験期間 | モジュール1,2 夏期:7月/冬期:12月 モジュール3 秋期:10月/春期:3月 |
| 受験資格 | モジュール1:誰でも受験可 モジュール2:モジュール1合格者(1,2の併願可) モジュール3:1,2の合格者のみ受験可 |
色彩技能パーソナルカラー検定は、1980年代から今日に至るまで日本でパーソナルカラーの普及に尽力されているトミヤママチコ(冨山眞知子)氏が立ち上げた団体による資格で、パーソナルカラーの基礎から実践までを体系的に学ぶことができます。
等級は、モジュール1からモジュール3までの3段階の"単位制"です。いきなり最上級のモジュール3を受験することはできず、まず初心者向けのモジュール1からはじめて、段階的に上を目指します。(初級と中級、モジュール1と2の併願はできます)
試験はCBT方式。会場を選び、試験センターに設置のパソコンから回答します。モジュール1と2の試験は7月と12月。上級のモジュール3は3月と10月の2回です。
色彩活用パーソナルカラー検定

色彩活用パーソナルカラー検定は、一般社団法人日本カラーコーディネーター協会(J-Color)が2010年から実施しているパーソナルカラーの資格です。同団体は色彩を暮らしに活かすための知識を学ぶ「色彩活用ライフケアカラー検定」も主催していて、色の知識を目的や用途に応じて実際に使いこなすための「色彩活用」の教育や提案を行っています。
| 名称 | 色彩活用パーソナルカラー検定 |
|---|---|
| 主催 | J-Color(一般社団法人日本カラーコーディネーター協会) |
| 備考 | 同団体の「色彩活用ライフケアカラー検定」もあり |
| 公式 | https://www.j-color.or.jp/paso/ |
| 等級制度 | 3級,2級,1級 |
|---|---|
| 受験方法 | 3級,2級:CBT方式 1級:会場でのペーパーテスト(PBT方式) |
| 試験方式 | 3級,2級:マークシート(多肢選択問題) 1級:マークシート & 配色実技+記述 |
| 受験料 | 3級:6,600円 2級:8,800円 1級:16,500円 (税込) |
| 試験時間 | 3級:60分 / 2級:80分 1級:135分(選択問題に50分、実技問題に事前説明+80分) |
| 試験期間 | 3級:通年 / 2級:偶数月 1級は年に1回(夏) |
| 受験資格 | 3級、2級は制限なし。1級は2級合格者のみ受験可 |
パーソナルカラーは、色の分類方法や判断基準が異なるいくつかの流派があります。そのなかで、J-colorの主催する「色彩活用パーソナルカラー検定」どの流派でも共通する理論を、基礎から応用まで総合的に学ぶことができます。
等級は3,2,1級の3段階。3級では色の基礎と「自己ブランディング」の方法を学び、2級は他者にブランディングのアドバイスを提案する方法を学びます。そして1級ではカラーコンサルタントとしてのスキルを習得します。
3級と2級はCBT方式。3級試験は通年で、いつでも受験できます。2級は2,4,6,8,10,12月の偶数月の開催。1級のみ夏に開催される試験会場でのペーパーテストで、選択問題のあと、配色実技(指示に沿って色見本を貼り付ける)の試験もあります。
色彩活用ライフケアカラー検定
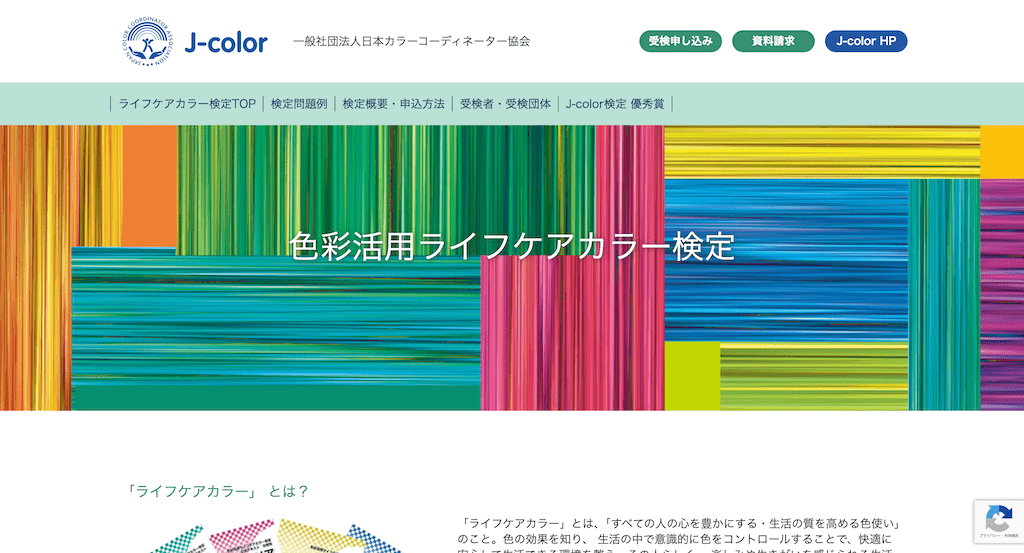
色彩活用ライフケアカラー検定は、既述の「色彩活用パーソナルカラー検定」と同じ、一般社団法人日本カラーコーディネーター協会(J-Color)が発行する色の資格です。J-Colorは「ライフケアカラー = すべての人の心を豊かにする・生活の質を高める色使い」と提唱し、色に関して広く学べる「色彩学」の資格と、「インテリア」「フード」「デジタル」の分野ごとの資格を出しています。
| 名称 | 色彩活用ライフケアカラー検定 |
|---|---|
| 主催 | J-Color(一般社団法人日本カラーコーディネーター協会) |
| 備考 | 同団体の「色彩活用パーソナルカラー検定」もあり |
| 公式 | https://www.j-color.or.jp/life/ |
| 等級制度 | 色彩学 分野別「インテリア」 分野別「フード」 分野別「デジタル」 |
|---|---|
| 受験方法 | IBT方式 |
| 試験方式 | マークシート(多肢選択問題) |
| 受験料 | 色彩学:4,400円 分野別はそれぞれ2,200円 併願:色彩学+分野別1つで併願する場合5,500円 (税込) |
| 試験時間 | 色彩学:40分 分野別はそれぞれ30分 |
| 試験時期 | 随時(サイトでご確認ください) |
| 受験資格 | 「色彩学」は誰でも受験可。分野別は「色彩学」合格者のみ受験可。 ただし「色彩学+分野別の一つ」で併願も可 |
J-Colorの定義によるライフケアカラーは、「すべての人の心を豊かにする・生活の質を高める色使い」を指します。色彩活用ライフケアカラー検定の等級は、この定義に基づいて色の基礎を習得する「色彩学」の資格を入り口とし、そのうえに「インテリア」「フード」「デジタル」の三つの分野を乗せた2段階制となっています。
インテリアは空間の配色調整、フードは食事・配膳にまつわる色、デジタルは人の視覚と見やすさの調整、IT領域における色使いなどを学びます。
受験者は、色彩学の資格を取得したあとに、各分野の資格を受験できます(色彩学と各分野1つを併願可)
試験方式はIBT方式、自宅やオフィスの自分のパソコンを用いて受験する方式で、開催は随時。サイト上に案内がありますので、チャレンジしたいタイミングでチェックしてみてください。ほかの資格に比べて受験料が安価な点も特徴です。
パーソナルカラリスト検定

パーソナルカラリスト検定は、「一般社団法人日本カラリスト協会」が2005年にスタートした、パーソナルカラーに関する資格です。この資格は、厚生労働省をはじめ、ブライダル文化振興協会、色彩環境福祉協会などいくつもの団体の後援を受けています。本資格では「人と色」に着目した、色彩知識と配色調和を身につけることを目指しています。
| 名称 | パーソナルカラリスト検定 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人日本カラリスト協会 |
| 備考 | 厚生労働省後援 |
| 公式 | https://colorist.or.jp/ |
| 等級制度 | 3級,2級,1級 |
|---|---|
| 受験方法 | PBT方式/CBT方式 3級のみ在宅ペーパーテストも可 |
| 試験方式 | 3級、2級、1級一次試験はマークシート(選択問題) 1級二次試験は配色実技+記述 3級在宅テストは選択、記述、論述、配色実技を実施 |
| 受験料 | 3級:7,700円 3級在宅:8,800円 2級:11,000円 1級:17,600円 1級一次または二次免除者:11,000円 (税込) |
| 試験時間 | 3,2,1級一次、二次すべて60分 3級在宅テストは160分 |
| 試験期間 | 年に複数回(サイトでご確認ください) |
| 受験資格 | 3級、2級は誰でも受験可。1級は2級合格者のみ。 |
パーソナルカラリスト検定はJPCAの「色彩技能パーソナルカラー検定」に次いで古いパーソナルカラーの資格です。厚生労働省をはじめ、日本ショッピングセンター協会、日本鉄道広告協会、日本ブライダル文化振興協会、日本ホビー協会、日本フローラルマーケティング協会、日本色彩環境福祉協会、など数々の団体が後援しています。
この検定試験のもっとも大きな特徴は、CUS(カラーアンダートーンシステム)という独自の表色系と配色理論に基づいて出題されること。この表色系では、色相、明度や彩度(色調)に加え、色をブルーアンダートーン(Bu)とイエローアンダートーン(Yu)という二つのアンダートーンに分類します。これらCUSへの正しい理解が合格のカギ。
等級は3,2,1級の3段階制で、ほかの試験と同じです。一方で受験方式は他に比べて柔軟であり、ペーパーテストと試験センターでのパソコンからの受験を選ぶことができます。さらに、3級は在宅でのペーパーテストも選択できます。1級試験はマークシートと実技の両方で基準点を超えれば合格です。
試験は年に複数回実施されます。
パーソナルカラー実務検定
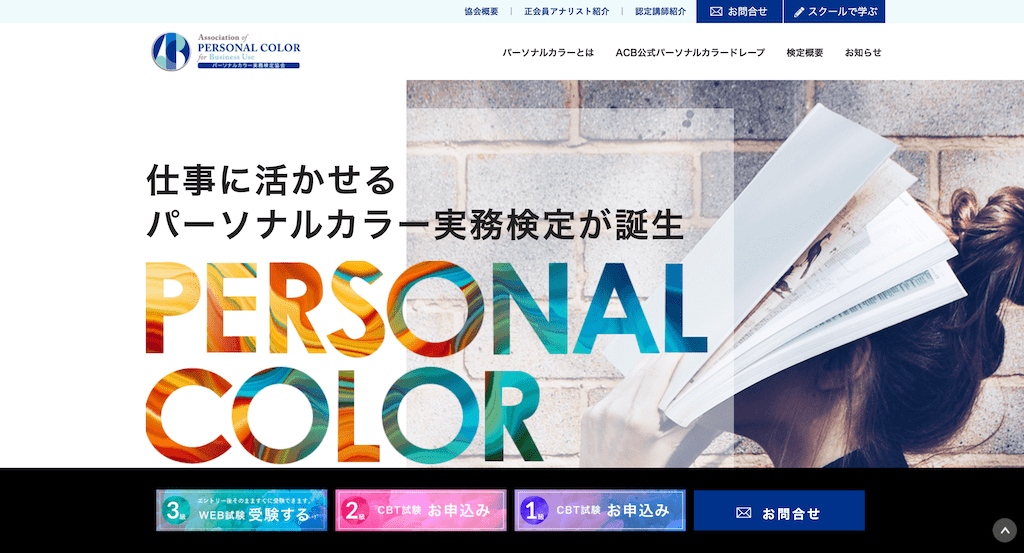
パーソナルカラー実務検定は、一般社団法人ICBIが主催するパーソナルカラー関連の色の資格です。正確な知識と正しい診断技術に基づいた現場で使える色彩知識の習得を掲げています。3級試験は自宅やオフィスのパソコンからいつでも受験でき、2級、1級も自分の都合にあわせてチャレンジできる柔軟性が魅力の一つ。
| 名称 | パーソナルカラー実務検定 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人ICBI(パーソナルカラー実務検定協会) |
| 公式 | https://acb-color.com/ |
| 等級制度 | 3級,2級,1級 |
|---|---|
| 受験方法 | 3級はIBT方式 2級、1級はCBT方式 |
| 試験方式 | マークシート(多肢選択問題) |
| 受験料 | 3級:2,200円 2級:7,700円 1級:13,200円 (税込) |
| 試験時間 | 3級:20分 2級:50分 1級:60分 |
| 試験期間 | 3級:自宅やオフィスからいつでも受験可 2級、1級:全国の試験会場でいつでも受験可(申込から最短3日後) |
| 受験資格 | 制限なし |
パーソナルカラー実務検定は、化粧品メーカー、化粧品ブランド、アパレル、宝飾メーカーやブランド、百貨店のような商業施設において活躍できるパーソナルカラーアナリストとして必要な知識の習得を目的とした資格です。
等級は3級、2級、1級の三段階制。3級は公式サイトから受験する簡単な入門的位置づけの資格。2級、1級はCBT方式で試験します。いつでも受験できるため、自分の都合にあわせて挑戦できます。
色彩士検定

「カラーマスター色彩士検定」は、全国美術デザイン教育振興会(ADEC:アデック)が1997年から主催する色の資格です。実績も長く、また文部科学省、財団法人日本色彩研究所などがこの資格を後援しています。3級、2級、1級の3つの等級で、基礎から実践まで幅広く色の知識を習得できます。公式サイトでは無料の4級、準3級などの腕試し的な試験も実施しています。
| 名称 | 色彩士検定 |
|---|---|
| 主催 | ADEC(全国美術デザイン教育振興会) |
| 備考 | 文部科学省、(財)日本色彩研究所、(財)専修学校教育振興会の後援 |
| 公式 | https://colormaster-shikisaishi.jp/ |
| 等級制度 | 3級,2級,1級 無料で試せる4級、準3級もあり |
|---|---|
| 受験方法 | 3級,2級はCBT方式 1級はPBT方式 |
| 試験方式 | 3級,2級は多肢選択問題 1級は理論(多肢選択式)と実技(プレゼンテーション作成)の2つ |
| 受験料 | 3級:6,000円 2級:7,500円 1級:20,000円 (税込) |
| 試験時間 | 3級:70分円 2級:90分 1級(理論):105分 1級(実技):130分 |
| 試験期間 | 3級:1月,9月(年2回) 2級:1月 1級:9月 |
| 受験資格 | 3級、2級は誰でも受験可(併願も可)。1級は2級合格者のみで、併願不可。 |
ADECの色彩士検定は、AFT色彩検定、東商カラーコーディネーター検定と並び1990年代にスタートした、文科省や日本色研などの後援を受けている信頼性の高い色の資格です。資格取得の過程で色について幅広く学習でき、日常生活から仕事まで、そしてデザイナーやアーティストを目指す人々にも役立つ色の専門知識を習得できます。
等級は3級、2級、1級の三段階制。1級は2級合格者のみ受験できます。3級試験のみ年2回、2級は1月、1級は9月の年1回の実施です。3級と2級は試験センターに行ってパソコンで受験するCBT方式。1級は試験会場でおこなうペーパーテストです。選択問題と、指示に沿って色見本を組み合わせて記述する実技試験をおこないます。
試験では、色彩検定とカーラーコーディネーター検定と同じくPCCSの色見本を用います。
デジタル色彩士検定
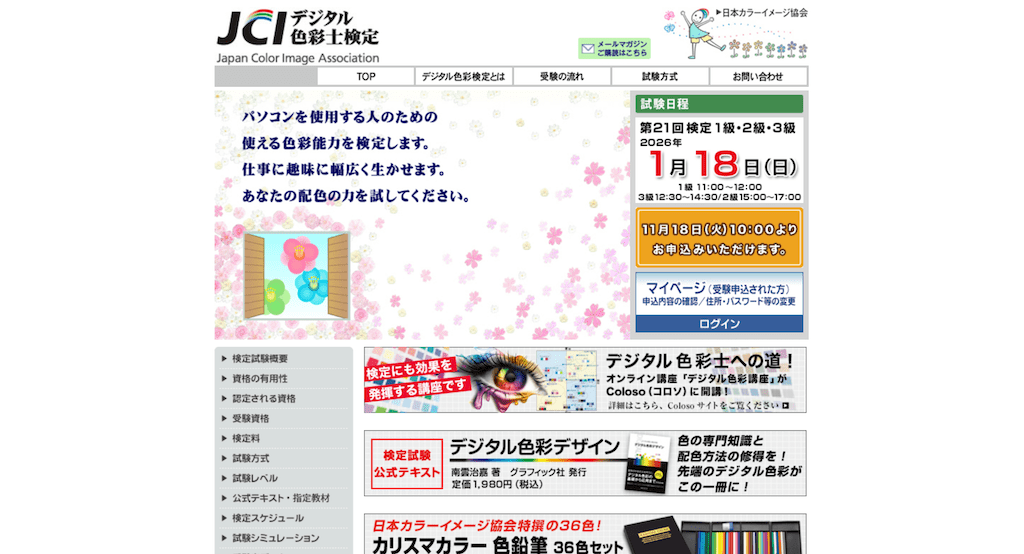
デジタル色彩士検定は、日本カラーイメージ協会(JCI)による色の資格です。文字どおりデジタル・WEBの色遣いに特化した知識の習得を目指しています。試験は、自宅やオフィス等のパソコンから、公式サイト上で受験する方式です。
| 名称 | デジタル色彩士検定 |
|---|---|
| 主催 | JCI(日本カラーイメージ協会) |
| 備考 | 特にWEBで使用する色彩に関して出題 |
| 公式 | https://www.j-color.jp/kt_index.php |
| 等級制度 | 3級,2級,1級 |
|---|---|
| 受験方法 | IBT方式 |
| 試験方式 | 多肢選択問題 |
| 受験料 | 3級:8,000円 2級:10,000円 1級:12,000円 (税込) |
| 試験時間 | 受験者ごとに異なります |
| 試験時期 | 随時(サイトにてご確認ください) |
| 受験資格 | 3級は誰でも受験可(ただしPCの扱いに慣れていること) 2級は3級合格者のみ、1級は2級合格者のみ受験可 |
デジタル色彩士は、従来の色の資格とは異なり、RGB(赤緑青)に基づくデジタルにおける発色と配色に中心に色の知識を習得するための資格です。色彩士検定と名がついていますが、ADECのカラーマスター色彩士検定とは別。日本カラーイメージ協会が2008年にスタートしました。
等級は3,2,1級。どの級も、自分のパソコンから受験するIBT方式。試験日の指定時間に公式サイトにログインして問題を解きます。パソコンをひととおり扱えることが受験の最低条件です。
3級は基本的なデジタル色彩の知識と配色能力が問われます。2級はデジタルカラーに特化したコーディネートについて出題され、1級は色彩計画、色彩戦略の立案など高度な知識について出題されます。
デジタル領域に特化しているという点で、ほかの資格とは異なる特徴も持つ色の資格です。
カラースタイルコンサルタント
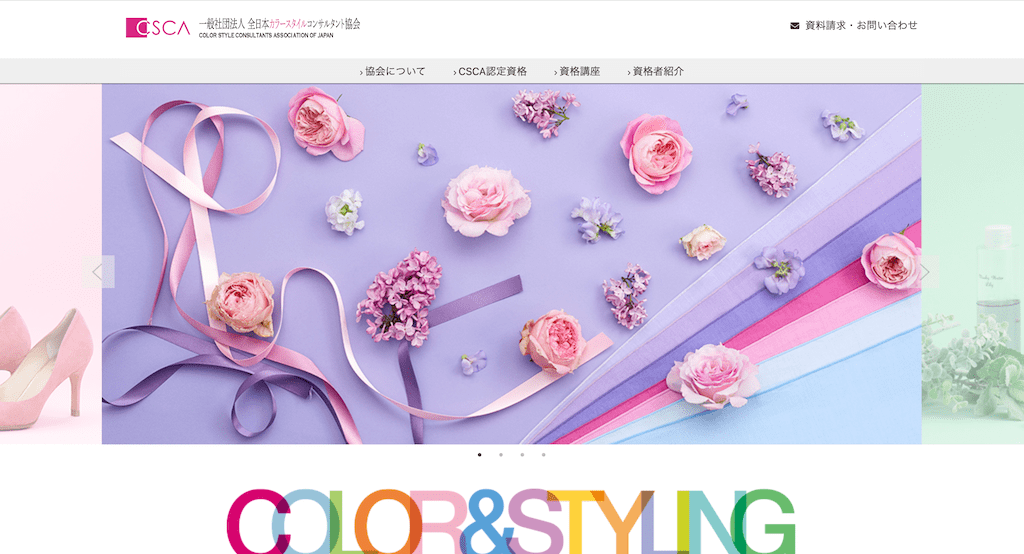
カラースタイルコンサルタントは、一般社団法人全日本カラースタイルコンサルタント協会(CSCA)が発行する色の認定資格です。色彩検定やパーソナルカラー検定など、ここまで挙げた各種資格のような一般受験の制度はなく、認定校や認定校士による講座で学んで習得します。イメージコンサルタントに必要なパーソナルカラーの基本的な知識をはじめ、表情、骨格、筋肉、立ち振る舞いなどを包括した独自の診断メソッドを学べます。
| 名称 | カラースタイルコンサルタント |
|---|---|
| 主催 | CSCA(全日本カラースタイルコンサルタント協会) |
| 備考 | 認定校・認定講師の講座を受けて取得 |
| 公式 | https://www.csca.or.jp/ |
| 等級制度 | 初級(3級) 中級(2級) 上級(1級, S級、SS級) CSCA認定講師 |
|---|---|
| 取得方法 | 認定校・認定講師の講座を受けて取得(他の資格のような試験はなし) |
| 受講料 | 受講料は認定校・講師により異なります |
| 講座時間 | 級ごとに異なります |
| 申込方法 | 公式サイトから問い合わせ |
カラースタイルコンサルタントは、単なる色の資格というより、スタイリングや身のこなしなどを含むイメージアップ全体に関する資格です。既述のとおり、テキストを買って独学で勉強して一般受験するといったシステムはありません。資格は、CSCAによる認定校、関連団体の16TPC認定校(16TPCは、16タイプパーソナルカラー協会の略)JSA-A認定校(JSA-Aは自分スタイル診断協会の略)のラピスアカデミー、そのほか認定講師の講座を受けて取得します。
認定資格のシステムは初級(3級)、中級(2級)、上級(1級、S級、SS級)、そして認定講師、認定校指導教員、指導教官という階層構造となっています。さらに、初級から上級までの各級内にも、受講内容に応じて取得できるディプロマの種類が異なります。たとえば、3級は「パーソナルスタイルコーディーネーター」と「パーソナルカラーコーディネーター」の講座・資格に分かれていて、両方の履修を終えると「カラースタイルコーディネーター」の資格を取得できます。
2級にも4つの講座があり、それぞれ資格名が異なります。上級は3種、認定講師になるための講座も3種。このように、いくつものステップに分かれているので、順番にチャレンジしていきたいといった方にとっては、嬉しいシステムかもしれません。
オーラソーマ資格認定講座

オーラソーマは、1983年にイギリスで誕生した、色を通じて人の内面を探究するためのヒーリングや精神的豊かさを目指すためのメソッドです。カラースタイルコンサルタントと同じで一般試験制度はありません。株式会社和尚アートユニティ(OAU)が主催する講座を受けて、英国オーラソーマアカデミーが発行するプラクティショナーの認定資格を取得します。
| 名称 | オーラソーマ資格認定講座 |
|---|---|
| 主催 | OAU(株式会社和尚アートユニティ) |
| 備考 | 一般試験はなく、講座を受けて資格取得 |
| 公式 | https://aura-soma.co.jp/course |
| 等級制度 | レベル1(初級コース) レベル2(中級コース) レベル3(上級コース) レベル3修了後に追加コースあり |
|---|---|
| 取得方法 | 所定の講座を受けて取得 |
| 受講時間 | 各レベル24時間(4日間)ずつ |
| 受講料 | 各レベル88,000円 |
| 受講時期 | 各レベル随時(サイトでご確認ください) |
| 申込方法 | 公式サイトから問い合わせ |
スピリチュアルやヒーリングに興味がある方は、オーラソーマという概念について耳にしたことがあるかもしれません。オーラソーマは、イギリスのヴィッキー・ウォールという女性が生み出した、色の力で人々の内的浄化や調和を図るためのメソッド。「イクイリブリアムボトル」という名称の、2色にわかれた美しい水が入ったボトルを120種類用いて、クライアントが選んだボトル(色)から内面を探り、問題解決をサポートします。
オーラーソーマは現在53カ国に普及していて、日本ではOAUが主催する講座(初級、中級、上級、それぞれ4日間)を受講することで、英国オーラソーマアカデミーが発行するプラクティショナーの認定資格を得られます。
つまり、この認定制度は色彩検定やパーソナルカラー検定など「色の知識を学ぶ」といった色の資格とはまったく方向性が異なります。非科学的で根拠がないと考える方もいるかもしれません。一方、効果を実感している方もいますから、色のもたらす力の不思議さ、おもしろさを感じられる一つの領域とも言えるでしょう。
色の資格を種類や試験方式などで比較
さて、このように色の資格試験や講座がいくつもあることをご覧いただいたところで、今度はこれらの資格を出題内容や試験方式などで仕分け・比較してみました。
資格の種類で分類
以下、色彩学や配色について包括的に習得できる資格、パーソナルカラーの理論に特化した資格、デジタル色彩が主題(あるいは対象として大きく触れている)の資格、ヒーリング関連の4種類に分類しています。
色彩知識全般
- 色彩検定
- カラーコーディネーター検定
- カラーマスター色彩士検定
- 色彩活用ライフケアカラー検定
パーソナルカラー
- 色彩技能パーソナルカラー検定
- 色彩活用パーソナルカラー検定
- パーソナルカラリスト検定
- パーソナルカラー実務検定
- カラースタイルコンサルタント
デジタル色彩
- カラーコーディネーター検定
- 色彩活用ライフケアカラー検定
- デジタル色彩士検定
ヒーリング
- オーラソーマ
色の基本的な知識は、どの資格でも学びます。そのうえで、ほかに比べてより広範囲にわたる理解を求められる資格を「色彩知識全般」としてカテゴライズしました。色彩検定、カラーコーディーネーター検定、カラーマスター色彩士検定は1990年代から実施されている権威性も高い資格です。
パーソナルカラーの資格は4種類。そこにカラースタイルコンサルタントの認定制度も加えています。デジタル上での色彩表現については、色彩検定でも学びますが、カラーコーディネーター検定やデジタル色彩士、色彩活用ライフケアカラー検定の分野別資格「デジタル」の方が専門的です。
受験方式で分類
現在、色の資格の受験方式には主に4つの方法が採用されています。資格と等級ごとに異なりますので、整理してみました。赤文字のカラーコーディネーター検定とパーソナルカラリスト検定は、CBT方式、IBT方式のいずれかを選んで受験できます。
CBT方式
CBT方式(コンピューター・ベースド・テスト):受験申込時に全国の試験センターから希望の場所を指定し、会場に設置しているパソコンで受験する方式。試験会場が選べることと、試験を受ける日も、指定期間中から自分の都合で調整できる点が魅力。
- カラーコーディネーター検定(全級)
- 色彩技能パーソナルカラー検定(全級)
- パーソナルカラリスト検定(全級)
- 色彩活用パーソナルカラー検定(3,2級)
- カラーマスター色彩士検定(3,2級)
- パーソナルカラー実務検定(2,1級)
IBT方式
IBT方式(インターネット・ベースド・テスト):自宅やオフィス、そのほか協会が定める受験に適した環境で、ご自身のパソコンから受験する方式。会場に行けない方でも受験可能。
- カラーコーディネーター検定(全級)
- 色彩活用ライフケアカラー検定(全級)
- パーソナルカラー実務検定(3級)
- デジタル色彩士検定(全級)
PBT方式
PBT方式(ペーパー・ベースド・テスト):協会が定める全国の試験会場にて、試験日に受験する方式。従来から実施されているペーパーテスト。
- 色彩検定(全級)
- パーソナルカラリスト検定(全級)
- 色彩活用パーソナルカラー検定(1級)
- カラーマスター色彩士検定(1級)
在宅ペーパー
在宅ペーパー:テスト問題が自宅に送付され、所定の条件のもとで受験する方式。
- パーソナルカラリスト検定(3級)
カラースタイルコンサルタント、オーラソーマは一般試験がありません。
どの色の資格が私におすすめ?
これだけ種類が多いと、「どの色彩資格が自分に合っているのかな?」と疑問が生じるのも無理はないですよね。
個人的な解釈となりますが、はじめて色の資格にチャレンジするなら色彩検定は最適だと思います。業界においてもっとも認知度が高いですし、色について包括的に学習できます。カラーマスター色彩士検定も同様です。
そこからさらに、製品パッケージや広告、インテリア、WEBデザインなどの領域において、実務的なノウハウと知識を深く学びたい方や、カラーコンサルタントとして独立を考えている方は、カラーコーディネーター検定の挑戦もおすすめです。カラーコーディネーター検定の試験は、色彩検定に比べると仕事に直結する実務手順についても出題されます。
アパレル、ブライダル、営業、そのほか「人」に直接関わってくる領域であれば、「似合う色」「状況に最適な色」の診断技術、提案力を身につける目的からパーソナルカラー検定にも挑戦してみてください。将来的にパーソナルカラーコンサルタントとして独立や副業を考えている方々にとっても、資格取得がその入り口となります。
パーソナルカラー検定を主催する各団体は、それぞれ流派・考え方が少しずつ異なります。順番にいくつか受験していけば、より客観的な診断ができるようになるでしょう。
そもそも色の資格は取るべき?役立つ?意味ない?
そもそも論として「色の資格って役立つ?資格をとって意味あるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。その点についてもお答えします。
就活に役立つ?履歴書に書ける?
「就活を有利にするために資格を取ろうか」と考えている学生の方も多いと思います。正直にお答えすると、履歴書に書くことはできますが、資格そのものに採用を左右するほどの力は期待できません。もちろん、無いよりはプラスであり、アパレル、繊維、インテリア、WEBデザイン、ブライダル、そのほか色を扱う業界であればより好印象を得られるでしょう。
特に「なぜ色の資格取得を考えたのか?」「資格取得の過程で学んだ色の知識が、仕事にどう活かせるのか?どう活用したいと考えているのか」を明確に説明できることが大切です。資格に挑戦した意図が明瞭で、しっかりアピールできるなら、就活に役立つと言えます。
とは言うものの、最初は「就職に有利かな?」といった下心や、「オシャレに見せたい!見られたい!」といった興味をモチベーションに学習し始めても全然良いと思います。学んでいくうちにおもしろくなってきたらしめたもの。就活をはじめる頃には「色の知識を仕事にどう活かせるか?」を、自分の言葉で自然と語れるようになると思いますよ。3級を取って辞めるのではなく、できれば2級や1級まで目指して、色への理解を深めてください。
副業や起業などの独立に役立つ?
色の資格が副業や独立起業において役立つかどうかは、就活よりもシビアです。資格を持っていることと、カラーコンサルタントとして生計を立てられるかは、まったく別物と考えてください。「XX検定1級」は肩書きとして信頼度のアップにはつながりますが、それだけです。
色が関わってくる領域で、個人で独立を目指せる仕事を挙げてみますと、ヘアスタイリスト、ネイリスト、メイクやスキンケアなどを指導するビューティーコンサルタント、それらにファッションコーディネートを含むイメージコンサルタント、インテリアデザイナー&コーディネーター、デザイナー、イラストレーター、WEBクリエイター、マーケター、インフルエンサーなどでしょうか。ほかにもたくさんあるかもしれません。少し規模が大きくなると、繊維や色材の取り扱い事業も、色が大きく関わってきますね。
このように列挙した仕事・職種・領域からお気づきかもしれませんが、どれも「色以外の」何か特別な技術や知識に基づいてサービスを提供することが前提で、色は価値を高めるための従属的なものです。
たとえばヘアスタイリストの場合、「髪を切る、整える」という技術ありきで、「似合う髪色」や「見せ方」の提案が成り立ちます。
要するに、色だけ単独でサービス化される領域は限られます。パーソナルカラリストは色の知識を直接的にサービスとして提供する仕事ですが、独立や副業を考える際には、色の知識以外のスキルも求められます。
つまり、「色の資格を取る → すぐに独立開業できる」とは言い難く、この発想だと道が限られます。
一方で、ほかの何かの仕事に「色の知識をプラスする」という発想なら道は大きく開けます。色の資格取得の過程で学ぶ知識は、同業他者との差別化を図れる、あなたの大きな強みになるでしょう。
なぜなら、色は暮らしのすべての領域に関わっていて、人の行動に影響を与えているため。
新しいサービスの追加による収益増、提案の説得力アップ、広告宣伝効果の向上、そのほか色々なメリットを得られます。
色の資格取得に意味があるのか?意味ないのか?無駄?という疑問は、この「色の影響と効果が及ぶ範囲があまりにも広すぎるので、資格単独で価値を見出しにくく、自分で活用方法を考えなければならい」という点からも生じているのだと思います。
色の資格を主宰しているそれぞれの団体には、認定講師という制度があります。1級(最上位)の資格を取って講師養成講座を受けると、その団体の講師として、各所で講演やセミナーに登壇できます。その道も独立の選択肢の一つと言えます。
現在、色の社会への影響と重要性に対する理解が高まってきていますから、活躍できる領域は拡大しています。「色の資格 = すぐに仕事に繋がる」とは言えませんが、アイディア次第で飛躍できる可能性は十分です。
仕事や趣味に役立つ?
お勤め先での今の仕事や、取り組んでいるプロジェクトに色の知識が役立つかどうか?という点では、それがどんなものであれ100%有効と断言できます。なぜなら色は人の感覚であり、既述のとおり暮らしの全体に関わるから。
一見関係がなさそうな領域でも、配色や照明を変えるだけでスタッフやお客様の行動が変化します。社会課題の解決にもつながるでしょう。
趣味においても、目的に応じて配色を工夫できる技術は、自分や周囲の満足感の向上につながります。
対象範囲が広すぎて曖昧な表現しかできませんが、学んだ知識が仕事や趣味に活かせて周りが満足している様子を見ると、「勉強して良かった!」「色って凄い!」と改めて実感しますよ。
色の資格の勉強方法|独学合格できる?講座は必要?
最後に、勉強のためのアドバイスを。
色の資格試験は、基本的には独学で合格できます。試験を受けるまでの勉強時間にもよりますが、公式テキストや問題集を活用し、学習スケジュールを立て、理解を深めていけば自力で1級合格を目指せます。
私は色彩検定の全級、カラーコーディネーター検定1級「商品色彩」(現在のスタンダードクラス・アドバンスクラスの二等級制になる前)、色彩技能パーソナルカラー検定のモジュール3(上級)を独学で取得しました。そのほかの資格は取得していませんが、各団体が発行する公式テキストはひと通り購入して目を通しています(趣味です)
それらの資格を取得した際のことを振り返ると、やっていたことは単純だったと思います。知識のインプット・アウトプットの繰り返しです。具体的には、テキストを黙読して、自宅で音読して(これが結構効果的)、気になる内容はノートに書き出して整理して、色見本を切ったり貼ったりして配色練習して、色の名前を覚えて、を何度も実践しました。
各テーマごとの内容を「自分が誰かに伝えるなら、どう説明する?」と、アウトプットを前提にしながら、テキストを読んでいました。読むだけの勉強は、インプット主体。詰め込んで終わりの知識は忘れやすく、活用しにくいです。ですから、人に伝えることを前提に学習しました。
勉強時間は、1日30分から、多い時は2時間ほど。「色」という好きなテーマの勉強であり、自分で1級を取ると決めてチャレンジしていましたから、モチベーションは落ちませんでした。
ただ、仕事が忙しかった日やお酒を飲みすぎた翌日などは、割り切って勉強せずリフレッシュ。
試験当日に問題をスラスラ解いているイメージ、1級の合格証が家に届いているイメージを持って淡々と勉強を進め、上記の3つの試験は2年ほどで全部取りました。
独学が向いている人・向いていない人の違いはあるかもしれません。独学で学べる方の特徴は、モチベーションを維持できる(資格を取る目的が明確)、自分で計画を立ててそのプランに沿って勉強できる(根気がある)などでしょうか。
独学では、自分の理解度を自分で測るしかありません。先生や勉強仲間がチェックしてくれませんから、客観的に自分を判断する力も必要です。そんな風に書くとものすごく大変そうですが、勉強そのものを楽しめるなら大丈夫。マイペースで取り組みたいなら独学が適していると思います。
一方で、専門の色彩講座を受けるメリットも数多くあります。オンライン講座や近隣の専門スクールで講座を受講した方が、人によっては理解が進みやすく、余計な回り道をしなくて済むかもしれません。
つまり、学習の時短になります。
私自身、表色系の種類ごとの説明や専門用語などは自分で理解するのに苦労しました。
このほか、講座の受講には「仲間と共にモチベーションを維持できる」「合格の喜びを共有できる」などの良さもあるでしょう。受講料はかかりますが、独学で難しいと考えるなら講座を探して受講することもご検討を。
そして、色の勉強をはじめたら、日常がすべて学びの発見となります。
これが色彩学習の一番の醍醐味です。
街の看板、案内、広告、店舗デザイン、アパレルショップ、スーパー、そのほか暮らしのあらゆるところで、色の効果を活用した工夫が施されていることに気づくようになるでしょう。机に向かってテキストを眺めるだけでなく、「色が自分の暮らしにどう関わっているか」を、ぜひ積極的に探してみてください。
学習そのものを日々楽しみながら、肩の力を抜いて気軽に挑戦してみてくださいね。
まとめ|色の知識は役立つし面白い
いかがでしょうか?色の資格の種類やそれぞれの特徴の比較、取得の意義、勉強方法など、何か参考になる部分はありましたでしょうか。
色の資格試験は、いくつもの民間団体が主催しています。色彩検定、カラーコーディネーター検定、パーソナルカラー検定など種類が多くて「どれを受験しようか」と迷ってしまうかもしれませんが、結論としてはどれでも自由に受験できます。
それぞれの資格に違った特徴と魅力がありますから、ご自身の目的にあわせて選んでみてください。まずは入門レベルの3級からはじめて、ステップアップを目指しましょう。
受験の申込方法(願書提出)は各団体の公式サイトに記載があります。基本的には公式サイトからの申請です。CBT方式の試験の場合は、CBTのサイトに移動して申し込ます。申し込み期間はそれぞれの資格と等級で決まっていますから、事前にチェックして試験をいつ受けるのかを決めて、余裕を持って学習スケジュールを立ててください。
色の資格は、「趣味として」「仕事に役立てる」「将来独立するときのプラスに」など、どんな目的にも役立ちます。
なぜなら、色は日常のあらゆる領域に関係してくるから。
色の知識を学ぶことで、「自分に似合う色がわかるようになった」「部屋が心地良くなった」「家族の笑顔が増えた」「配色のスキルが上がってお客様の満足度が向上した」「売上が伸びた」など、想像以上にさまざまなポジティブな結果をもたらします。
学んだ知識をしっかり活用できれば、資格そのものが肩書としても役立つはず。
このページの情報は各団体の試験情報を随時見直してアップデートしますので、「色の資格にチャレンジしようかな」と思い立った際にお役立てください。
あなたの合格を、心から応援しています!
